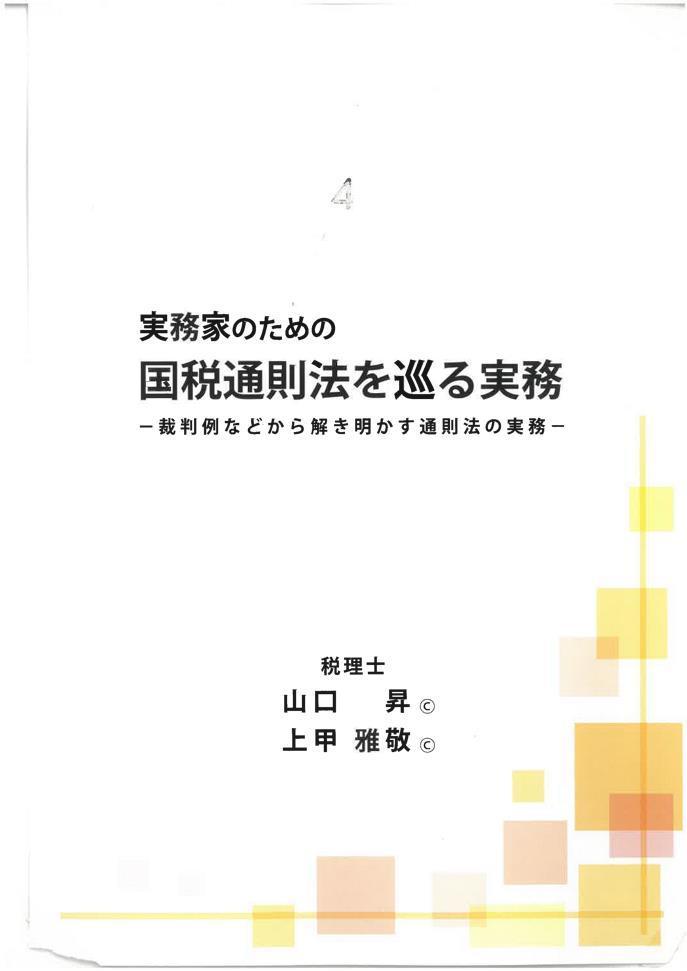vol.157(since 07/01/07〜)
17/07/12
不動産を売却すると、その譲渡益に対して譲渡所得税が課されます。
譲渡益は、譲渡価額−取得費−譲渡費用 で計算します。
例えば、
・Aさんは、B市内の自宅(土地建物)を平成29年1月1日に4000万円で売却した
・この自宅は、平成元年に7000万円(土地5000万円・建物2000万円)で購入した
・建物の減価償却費1500万円、譲渡費用は200万円とします。
この場合の譲渡益は
譲渡価額4000万円−取得費5500万円(土地5000万円+建物2000万円‐減価償却費1500万円)
−譲渡費用200万円=△1700万円
となり、譲渡益がマイナスのため譲渡所得税は課されません。
ところがこの自宅を取得した平成元年の確定申告で、Aさんが「収用の特例(収用等に伴い代替資産等を取得した場合の課税の特例)」を受けていた場合はどうでしょうか?
Aさんは、今回売却したB市内の自宅に住む前は、C市内の旧自宅(Aさんの亡父から相続により取得)に住んでいました。その旧自宅が平成元年に道路拡張によって市に収用され、C市から交付された補償金でB市内の自宅を購入していたのです。
そうすると、Aさんは平成元年に確定申告が必要となります(収用補償金は、原則として譲渡所得の収入金額となります)。
平成元年、収用時の旧自宅の収用価額や取得費は、以下の通りでした。
・収用価額(受取補償金)7000万円
・取得費350万円(購入価額不明のため、概算取得費7000万円×5%)
・譲渡費用は250万円
そうすると、譲渡益は
譲渡価額7000万円−取得費350万円−譲渡費用250万円=6400万円
となり、もし特例を使わない場合、Aさんはこの譲渡益に対する譲渡所得税を平成元年に支払っていたことになります。
しかしこの譲渡が「収用の特例」の要件を満たしていたため、Aさんは確定申告により特例を受け、この譲渡益に対する税金を繰り延べていたのです。
重要なのは、この特例はあくまでも課税の「繰延べ」であり、決して「非課税」ではない、という点です。
「繰延べ」とは、「今回は課税しませんが、将来その代替資産を売却した時には課税しますよ」という意味です。
今回のケースでは、平成29年にAさんがB市内の自宅(=代替資産)を売却した時に、平成元年に繰り延べていたC市内の旧自宅の譲渡益に課税しますよ、ということになります。この場合、譲渡益の計算をする際の取得費は、その自宅の実際の購入金額ではなく、旧自宅の取得費を用いることになります
具体的には、取得費は実際の購入価額7000万円ではなく、旧自宅の取得費として平成元年に申告した600万円(350万円+250万円)から、建物の減価償却費(仮に100万円とします)を控除して計算します。
そうすると、譲渡益は、
譲渡価額4000万円−取得費500万円(600万円−100万円)−譲渡費用200万円=3300万円
となり、平成29年の確定申告において譲渡所得税が課されることになります
なお、税務署はこの資産が特例を受けている資産かどうか事前に教えてはくれません。数十年前の処理を、自分で覚えておく必要があります。
大赤字だと思っていた譲渡所得が、過去に納税を繰り延べていたことによって多額の税金を支払うことになった・・・・・
収用の特例は課税の「免除」ではなく「繰延べ」なので当たり前のことなのですが、売ったときにそのことを誰も教えてくれず、自ら覚えておかないといけない、というのは制度上の欠陥という気がします。税務署はAさんが不動産を譲渡したことを把握できるのですから、何らかの方法でその情報を開示すべきと思います。
とはいえ、現行制度では自分で覚えておく以外に対処法はありません。「収用の特例」のほかに、「買換えの特例」も同様です。以前住んでいた家を買い換えているような場合、特例を使用していないかどうか確認しましょう。
「毎月の訪問、毎月の報告、毎月の安心」
上甲会計は、お客様の経営を徹底的にサポートします!
上甲会計事務所 http://www.jokokaikei.net